エコジオ工法FAQ
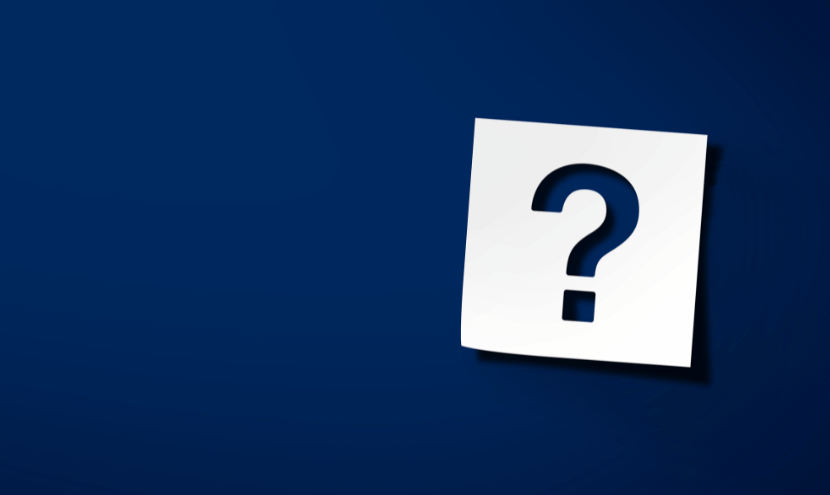
一般
砕石だけで大丈夫? セメントや薬品を混ぜて固めるのでしょうか?
何も混ぜずに、砕石だけで施工します。
エコジオ工法は、基本的な施工装置を国立大学法人三重大学との共同研究で開発し、(財)日本建築総合試験所より「建築技術性能証明」を取得しております。
セメントを使う方法や、鉄の杭を使う方法は今でも多く使われていますが、最近は、砕石を用いる地盤改良技術も増加しています。エコジオ工法は、平成30年3月末時点で、8,915件の施工実績があり、全国規模の住宅会社などでも使われています。
また、万が一の不等沈下などの場合に、その保証を行う地盤保証会社については、国内大手7社の保証対象工法として認められています。
エコジオ工法と、エコジオZERO工法の違いは?
エコジオZERO工法は、残土がほとんど出ません。
エコジオ工法は、直径42㎝のスクリュー付のケーシングで掘削し、ケーシングの体積と同程度の土砂を地上に排出します。一方、エコジオZERO工法は、直径32㎝のスクリューのついていないケーシングを地中に圧入するため、土砂がほとんど排出されません。この2つは、土質や現場周辺環境など様々な条件により使い分けています。
今は、エコジオZERO工法が増える傾向にあります。
どれくらいの重さまで支えられますか?
建築技術性能証明では、最大で100kN/m2としています。
改良できる深さは?また直径は?
地表面から最大5.0mまでです。
直径は、エコジオ工法が420㎜、エコジオZERO工法が320㎜です。
柱状改良、杭工法で設計長が5mを超えるのですが、エコジオ工法は使えますか?
使えることはあります。
エコジオ工法は、杭ではありません。上からの荷重を分散させるため、固形杭(柱状改良、杭工法等)のように強固な支持層を必要としません。他の工法で設計長が5mを超える場合でも、エコジオ工法の設計長が5mより短くなることはよくあります。適用できるかどうか、設計長がどうなるかは、地盤調査データなどがあればわかります。
施工
セメントや杭なども含め、どの工法が一番強いのでしょうか?
どの工法も不等沈下の防止を目的として必要なだけの補強を行うので、強さに違いはありません。
建物の条件に対して過剰な設計は経済性が劣ります。また、地形や土質条件によって各工法の向き不向きはありますので、それらを考慮して工法を選定することがより重要です。
どんな地盤で施工できますか?
粘性土・砂質土・ロームが適用範囲であり、あまり土質は選びません。
ただし、大きめのガラや玉石などの掘削の障害となるものが多い地盤、地中の軟弱層のバラツキが多い地盤には向きません。また、腐植土の存在する地盤については沈下の予測ができないため、適応不可としています。
詳しくは、お問い合わせいただくか、「建築技術証明」のページをご覧ください。
→「建築技術証明」のページへ
適用条件
他の工法と比べ、土地の価値への影響は?
他の工法に比べ、影響は少ないと思われます。
土地の価格の算定基準(不動産鑑定評価基準)では、地中の埋設物や土壌汚染は、その撤去費用を割り引いて算定されます。従来工法では、セメントや鉄の杭を地中に埋め込みますが、エコジオ工法では砕石だけです。
最近、借地などは土地を返還する場合に、地盤改良による地中の構造物の撤去費用でのトラブルが増えているようです。近年は撤去が決まっている仮設施設や撤去の可能性があるコンビニやチェーン店などの店舗からの問い合わせや、採用が増加しています。
エコジオ工法は、どの地盤保証会社で保証を受けられますか?
下記の地盤保証会社(7社)から保証対象技術として認められています。
ジャパンホームシールド
ハウスワランティ
GIR
地盤ネット
在住ビジネス
地盤審査補償事業
ハウスジーメン
住宅用の砕石地盤改良技術の中では、最も多くの保証会社から保証を受けられる工法です。
事前の地盤調査は、どのような調査が必要ですか?
スウェーデン式サウンディング試験を標準としています。
その他の試験方法についてはお問い合わせください。
見積りをしてもらうにはどうすればいいですか?
お問い合わせフォームからご連絡ください。その際に下記のものがそろっているとスムーズに進みます。
1. 地盤調査報告書 2. 基礎伏図・基礎断面図 3. 平面図
4. 敷地配置図 5. 立面図
施工可能なエリアは?
北海道、沖縄、離島以外の日本全国で対応できます。
エコジオ工法のデメリットは?
下記の地盤条件で適用できないことです。
・腐植土を含む地盤。
・新たに造成された、盛土直後(3ヵ月以内)の地盤。
・切土部と盛土部が混在する、造成された地盤。
・地中の支持層の傾斜が急な地盤。
・崖条例により、杭での施工が必要な地盤。
品質管理
砕石をどのように締固めるのでしょうか?
ケーシング先端のスクリューを回転させることで締固めを行います。
さらに均質な締固めを行うために一度に締め固める砕石の厚さや締め固め力(回転トルク)に規定を設けています。
※詳しくは「施工方法」を参照してください。
施工時に騒音や振動は発生しませんか?
騒音や振動が少ない工法です。
地盤改良機とバックホーのエンジン音、アタッチメントの回転時の音が出ますが、大きな音ではありません。砕石の締固めに振動は使わないため、施工中に近隣へ振動による影響はありません。
施工する業者、オペレータによって、品質に差がでるのでは?
「品質に差がないこと」がエコジオ工法の大きな特徴です。
エコジオは、10㎝の層厚で、一定の圧力で砕石を締固めます。施工では、オペレータは施工管理装置のアラームにより操作を行い、10㎝毎に砕石を締固めた圧力が記録されます。そのため、初心者と熟練したオペレータでの施工の品質に差はありません。
また、他の砕石工法では備えていない、一連の砕石の締固めを自動で行う「自動砕石締固め機能(業界初)」も備えています。
ちゃんと施工できているか、確かめる方法はありますか?
施工後に報告書(施工管理装置の記録を含む)をお渡ししております。
施工管理装置により、補強体一本ごとに掘削した深度、砕石の使用量、締固めトルクを計測して記録しています。この記録は、暗号化されているため改竄の恐れがありません。そして、本部のサーバーを通して保存・解析・帳票化が行われます。報告書には、建築技術性能証明書で規定した通りに施工されているか確認がされています。
事後の強度試験(平板載荷試験など)は、行いますか?
行いません。
エコジオ工法は、施工中に10㎝毎に投入した砕石量や砕石を締固めた圧力(回転トルク)を計測しています。5.0mの砕石補強体なら50回計測し、すべて施工管理装置で記録されています。この記録により砕石の密度が十分高まり、設計で求められている強度が確保されていることが確認できます。すなわち、強度を確認しながら施工しているということです。このことは、建築技術性能証明で認められています。
液状化対策
エコジオ工法で確実に液状化を防止できますか?
現在、確実に防止できる技術は存在しないと思われます。
ただし、砕石は以前からグラベルドレーン工法として大型の土木工事などで使われており、液状化抑制効果が確認されています。地盤条件、設計方法にもよりますが、エコジオ工法もグラベルドレーン工法と同様にケーシングを使い連続した砕石パイルを構築するため、同様の効果を期待することはできます。
エコジオ工法の施工実績が知りたいです
平成30年3月末までの、全国での施工件数は8,915件です。
住宅の地盤補強の実績が主ですが、他には公共施設の液状化対策や、地下水の排水対策としても使われています。
公共工事に使われていますか?
仮設校舎、介護施設などの地盤補強、東日本大震災の被災地での液状化対策、高速道路の盛土内地下水の排水対策に使われています。
住宅の地盤改良でエコジオ工法を使う予定ですが、同時に液状化対策が図れるのですか?
支持力補強とは別に液状化対策としての設計が必要です。
一般的に住宅が傾かないように行う地盤改良は、支持力補強であり支持力や沈下に関しての設計検討を行います。液状化対策を行うためには砕石杭をドレーンとして利用する「間隙水圧消散工法」としての設計を行いますので、全く別の設計検討となります。必要な調査データも支持力補強とは異なり、より詳細な地盤調査を必要としますので、詳しくはお問合せ下さい。
価格
他の工法と比べて、どのような場合に安くなりますか?
主に支持層が深い場合、地盤改良工事費が高い場合に安くなります。
エコジオ工法は支持杭ではないので、堅固な支持層を必要としません。そのため、支持杭で必要とする硬い層が深いところにある地盤では、設計改良深度の差が大きくなり、施工費が安くなる傾向があります。
また、エコジオ工法は砕石のみを使用するため、撤去費用まで含めたライフサイクルコストとして考えると、非常に経済的です。










